資料ぶろぐ
まちづくりの著書や資料
ENTRY NAVI
- Home
- 紹介
- 2025-07-18 [PR]
- 2014-11-12 長谷川名誉教授の講演 渡辺利明
- 2013-08-11 もういい会喜寿記念 作品展
- 2008-08-31 東京山の手物語
- 2007-12-27 静岡県75歳以上10%超
長谷川名誉教授の講演 渡辺利明
長谷川名誉教授の講演 渡辺利明
長谷川徳之輔・明海大学名誉教授は、四小、四中、東高を卒業。昭和三十四年に東北大から建設省に入省、国の建設行政の中核に身を置き、戦後経済、社会資本のあるべき姿などを研究し、六〇年代の不動産を中心としたバブル経済の進行に対し、いち早く警鐘を鳴らし、当時はNHKや民放番組に解脱者として連日駆り出されていた。
バブルに手を貸した不動産業、ノンバンク、金融機関の経営姿勢を厳しく糾弾する彼とは、当時銀行に席を置いた私は、よく議論を交わした。しかし、その後の事態の推移を見れば、北海道拓殖銀行、日本長期信用銀行の倒産など激変が続き、我が国経済は「失われた二十年」と冒われる経済の低迷を受けて現在に至っている。
最近、ようやく全国レベルで問題化しつつある「地方の衰退化問題」について、彼は生まれ故郷沼津の鉄道高架事業を具体的事象として取り上げ平成二十年、『衰退し続ける地方都市再生の道をさぐる』を出版したが、これより以前から、建設経済にかかる豊富な体験かち沼津駅付近鉄道高架事業の抱える問題点を鋭く指摘していた。これまで何回となく川勝平太知事、栗原裕康市長、地域有力者らに問題提起してきたが、中央官庁に長く携わってきた彼にすれば、この事業はバブル期に企図されたもので、これに固執していることが沼津衰退の一因と捉えている。知事、市長に、この事業の基本的問題を直視するよう提言してきたが、何の反応もないという。
また、高校、建設省の後輩である櫻田光雄氏、斎藤衛氏が、かつて市長の座を争い、長谷川名誉教授は二人の先輩の立場から、「この間題について市民のために、どうすれば良いのか」建設のプ回として十分話し合うよう求めたが、二人とも聞く耳を持たなかった。また二人が、この問題に深く関わって来たのに、何の発言も、弁解もしていないことに失望しているという。
知事は難航する原地区への貨物駅移転を前提に,鉄道高架事業実施の腹を固めたようだが、移転用地の確保には、これから何年掛かるか分からない。ましてや高架事業の完成までには十五年から二十年、あるいは何十年先のことになるのかも知れない。
長谷川名誉教授は、事業目的であった沼津駅の南北交通渋滞は既に解消されているのだから、として現在の不便な状態を解消するために沼津駅に自由通路、さらに、これを幅約一〇〇㍍ぐらいに拡大して八千平万㍍程の空中空間の建設を提唱している。これなら人やベビーカー、車椅子、自転車などが自由に南北を通行できるようになり、問題は一挙に解決するという。この空中空間の上に他に何を設けるかは検討しなければならないが、空中空間そのものは三十億円程度で出来るだろうとし、鉄道高架事業と異なり短期、ローコストの建設が可能だという。
実は、この提案は(昨年のPI委員会でも取り上げられたものだが、十四日の講演では、この問題を中心に脱明したいという。
講演では、沼津市、三島市、長泉町、清水町、函南町は、人の交流、経済活動などで一つの地域として形成されており、この観点からの取り組みが必要であることを指摘したいといい、具体的なデータなどを墓に、沼津が現在の低迷から脱する処方箋が示されると思う。
十四日の講演には、沼津の未来に関心を寄せる多数の方々の来場をお願いする次第です。聴講は無料です。
時間は午後七時から八時四十分。会場は市立図書館四階の視聴覚ホール。(下石田)
(沼朝平成26年11月12日「言いたいほうだい」)
長谷川徳之輔・明海大学名誉教授は、四小、四中、東高を卒業。昭和三十四年に東北大から建設省に入省、国の建設行政の中核に身を置き、戦後経済、社会資本のあるべき姿などを研究し、六〇年代の不動産を中心としたバブル経済の進行に対し、いち早く警鐘を鳴らし、当時はNHKや民放番組に解脱者として連日駆り出されていた。
バブルに手を貸した不動産業、ノンバンク、金融機関の経営姿勢を厳しく糾弾する彼とは、当時銀行に席を置いた私は、よく議論を交わした。しかし、その後の事態の推移を見れば、北海道拓殖銀行、日本長期信用銀行の倒産など激変が続き、我が国経済は「失われた二十年」と冒われる経済の低迷を受けて現在に至っている。
最近、ようやく全国レベルで問題化しつつある「地方の衰退化問題」について、彼は生まれ故郷沼津の鉄道高架事業を具体的事象として取り上げ平成二十年、『衰退し続ける地方都市再生の道をさぐる』を出版したが、これより以前から、建設経済にかかる豊富な体験かち沼津駅付近鉄道高架事業の抱える問題点を鋭く指摘していた。これまで何回となく川勝平太知事、栗原裕康市長、地域有力者らに問題提起してきたが、中央官庁に長く携わってきた彼にすれば、この事業はバブル期に企図されたもので、これに固執していることが沼津衰退の一因と捉えている。知事、市長に、この事業の基本的問題を直視するよう提言してきたが、何の反応もないという。
また、高校、建設省の後輩である櫻田光雄氏、斎藤衛氏が、かつて市長の座を争い、長谷川名誉教授は二人の先輩の立場から、「この間題について市民のために、どうすれば良いのか」建設のプ回として十分話し合うよう求めたが、二人とも聞く耳を持たなかった。また二人が、この問題に深く関わって来たのに、何の発言も、弁解もしていないことに失望しているという。
知事は難航する原地区への貨物駅移転を前提に,鉄道高架事業実施の腹を固めたようだが、移転用地の確保には、これから何年掛かるか分からない。ましてや高架事業の完成までには十五年から二十年、あるいは何十年先のことになるのかも知れない。
長谷川名誉教授は、事業目的であった沼津駅の南北交通渋滞は既に解消されているのだから、として現在の不便な状態を解消するために沼津駅に自由通路、さらに、これを幅約一〇〇㍍ぐらいに拡大して八千平万㍍程の空中空間の建設を提唱している。これなら人やベビーカー、車椅子、自転車などが自由に南北を通行できるようになり、問題は一挙に解決するという。この空中空間の上に他に何を設けるかは検討しなければならないが、空中空間そのものは三十億円程度で出来るだろうとし、鉄道高架事業と異なり短期、ローコストの建設が可能だという。
実は、この提案は(昨年のPI委員会でも取り上げられたものだが、十四日の講演では、この問題を中心に脱明したいという。
講演では、沼津市、三島市、長泉町、清水町、函南町は、人の交流、経済活動などで一つの地域として形成されており、この観点からの取り組みが必要であることを指摘したいといい、具体的なデータなどを墓に、沼津が現在の低迷から脱する処方箋が示されると思う。
十四日の講演には、沼津の未来に関心を寄せる多数の方々の来場をお願いする次第です。聴講は無料です。
時間は午後七時から八時四十分。会場は市立図書館四階の視聴覚ホール。(下石田)
(沼朝平成26年11月12日「言いたいほうだい」)
PR
東京山の手物語
「東京山の手物語」長谷川徳之輔著
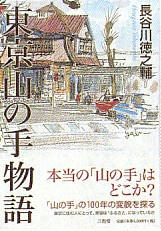
駿府といえば徳川、徳川といえば江戸というわけでもないが、今回は江戸・東京の本。むろん縁が深いからといつて、静岡の皆さん全員が東京に関心を持たれているわけではないだろうが、本書は東京という地域の特殊性を越えて、日本の近代化の過程を象徴する物語にもなっている。そこが面白い。
著者は旧建設省出身の土地問題の専門家。長年にわたって東京という都市を実地見聞と研究の両面で見つめ続けてきた人だけあって、地をはうアリの目と空から眺め下ろす鳥の目とを駆使して巨大都市の変ぼうを活写してゆく。
東京の「山の手」は歴史とともにどんどん西に移ってゆくのだが、その近代100年の膨張を追うように、最新の都心である話題の六本木ヒルズに始まり、かつて郊外であった渋谷・新宿を経て、東京南郊の品川・大崎に至る各地の歴史が、さまざまな逸話を織り交ぜて語られる。
その話題の一つ一つが興味深いが、それにとどまらず、やがて読者は近代日本が手に入れたものと失ったものとの双方に向き合うことになる。
現在の千代田区・中央区・港区の範囲にすぎなかった江戸が、100年で世界有数のメガロポリス東京になるまでの物語。近代日本の光と影を凝縮したかのような、極端に陰影の深い歴史物語であることを本書は示している。著者は最後に問う。東京に住む人にとって、東京は「ふるさと」になっているか、と。
図版も多く、東京の人だけでなく全国の歴史好き、都市論好きの人にお薦めしたい好著だ。(三省堂・1575円)
(静新平成20年8月31日「お薦めの一冊」)
駿府といえば徳川、徳川といえば江戸というわけでもないが、今回は江戸・東京の本。むろん縁が深いからといつて、静岡の皆さん全員が東京に関心を持たれているわけではないだろうが、本書は東京という地域の特殊性を越えて、日本の近代化の過程を象徴する物語にもなっている。そこが面白い。
著者は旧建設省出身の土地問題の専門家。長年にわたって東京という都市を実地見聞と研究の両面で見つめ続けてきた人だけあって、地をはうアリの目と空から眺め下ろす鳥の目とを駆使して巨大都市の変ぼうを活写してゆく。
東京の「山の手」は歴史とともにどんどん西に移ってゆくのだが、その近代100年の膨張を追うように、最新の都心である話題の六本木ヒルズに始まり、かつて郊外であった渋谷・新宿を経て、東京南郊の品川・大崎に至る各地の歴史が、さまざまな逸話を織り交ぜて語られる。
その話題の一つ一つが興味深いが、それにとどまらず、やがて読者は近代日本が手に入れたものと失ったものとの双方に向き合うことになる。
現在の千代田区・中央区・港区の範囲にすぎなかった江戸が、100年で世界有数のメガロポリス東京になるまでの物語。近代日本の光と影を凝縮したかのような、極端に陰影の深い歴史物語であることを本書は示している。著者は最後に問う。東京に住む人にとって、東京は「ふるさと」になっているか、と。
図版も多く、東京の人だけでなく全国の歴史好き、都市論好きの人にお薦めしたい好著だ。(三省堂・1575円)
(静新平成20年8月31日「お薦めの一冊」)
静岡県75歳以上10%超
75歳以上が初の10%超 県年齢別人口
2007/12/27 (静新webnews)
県は26日、10月1日現在の県・市町別年齢別人口の概要を発表した。75歳以上の割合が10・2%と初めて10%を超えた一方、年少人口割合(15歳未満)が14・0%と前年から0・1ポイント減少するなど少子高齢化がさらに進む実態を示した。平成17年国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳と外国人登録原票に基づく移動数を加減して算定した。
老年人口(65歳以上)は83万1624人で、総人口に占める割合は21・9%と前年から0・7ポイント上昇した。このうち、75歳以上の人口は38万8168人。国全体の75歳以上の推計人口の割合は総務省の10月1日現在の統計調査で9・9%で本県はこれをやや上回った。
県内の生産年齢人口(15―64歳)は242万9251人(64・0%)と前年比0・6ポイント減。年少人口は53万883人。
市町ごとに年齢別人口をみると、65歳以上の老年人口割合が最も高いのは川根本町の40・4%。最も低いのは裾野市の17・3%で23・1ポイントの差がある。老年人口割合は西伊豆町(38・2%)、松崎町(35・7%)、南伊豆町(35・6%)など伊豆、川根地域で高くなっている。
年少人口割合が最も高いのは清水町の16・5%、最も低いのは熱海市の9・0%。生産年齢人口割合は最高が裾野市の67・7%、最低が川根本町の49・9%。
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
[07/21 真実勇蔵]
最新記事
(05/11)
(04/07)
(11/29)
(09/19)
(06/16)
